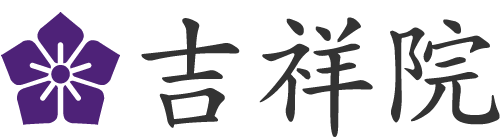やまと心を詠ずる歌
一般的にご詠歌と呼ばれるものは、詳しくは「ご詠歌」と「和讃」とに分けられます。ご詠歌は五・七・五・七・七の三十一文字からなる和歌・道歌(道徳・訓戒を分かりやすく詠んだ短歌)に曲を付けたもの。和讃は七五調、または五七調で作詞されたものに曲を付けたものです。このご詠歌と和讃の二つを一緒にして「ご詠歌」といいます。
まず、ご詠歌の起源は、花山(かざん)法皇(九八六~一〇〇八年)の西国巡礼までさかのぼります。花山法皇は十九歳で出家得度されました。ご自身は修行のため、西国観音霊場(近畿一円に広がる日本最古の霊場)の再興を願って巡礼し、その霊場にちなんだ和歌を奉納されました。それが大衆に親しみやすい節回しの巡礼歌となり、人々に唱えられたのです。
次に和讃は、七五調四句一章を基本とするもので、真言宗の宗祖・弘法大師空海の御作と伝えられる「いろは歌」が最も古い和讃と伝えられています。そして、和讃の節回しは声明が起源といわれ、各地の民謡などと交わりご詠歌の原点となる巡礼歌の旋律を生み出しました。むずかしくなじみにくい声明は、仏教を信じ、支えとする人々が増えるにつれ、誰もが親しみやすく仏の教えに接する機会を求め、いつしか和讃にかたちを変えていったのです。
人は生きていれば誰もが不安や恐れを抱え、思いどおりにならない苦しみにあえぎます。そして、なにかにすがり、支えともなるものを求めずにはいられません。仏さまの大いなる慈悲の心に救いを求めて手を伸ばします。そのように救いを求める心を歌に変えたのが、日本の大衆音楽のひとつ、ご詠歌です。ですから、密厳流のご詠歌は、日本人が培ってきた心をそのままに、みずみずしく表しているわけです。
仏さまの教えをわかりやすく説き、仏さまの世界を讃えるために、密厳流のご詠歌は多くの詠歌・和讃を育みました。密厳流は誰もが自然と口ずさめる音階を基本として、伝統的な詠歌・和讃の調べを脈々と受けついでいます。底のない悲しみに沈んだ心をいやす響き。さらに、仏の世界を実感して、仏に出会えた無上の喜びをたたえる旋律。日本人の奥底に眠る魂をゆさぶる音の連なり……それが密厳流ご詠歌の響きなのです。