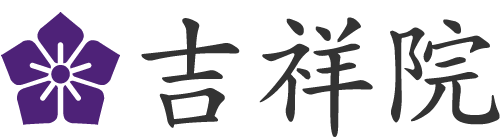やまと心を詠ずる歌
いま、私たちの暮らしのそこかしこに音楽があふれます。歌謡曲・演歌・愛唱歌・童謡・ポピュラー・クラシック・ジャズなどなど……多くの老若男女がいりろな歌を口ずさみ、カラオケで歌声を披露します。これほどさまざまな音楽があっても、日本人の誰もが心に響く音色、なつかしさに胸がしめつけられ、感極まる音楽があります。さて、それはどんな響きを持つのでしょうか。
ところで、日本の音楽の源流は、仏教音楽、つまり、お坊さんがお唱えする声明(しょうみょう)と言われています。この声明が元となって、日本のさまざまな音楽・節回しが生まれました。声明は、仏教の経文をお唱えする際に付けられた声楽(せいがく)で、インドで起こり、中国を経て日本に伝来しました。日本では、謡曲や浄瑠璃、浪花節や民謡などに大きな影響を与えました。
その声明は、お経を唱えるためのものなので、意味や内容を理解するのがなかなかむずかしく、旋律も一般の大衆にはなじめないものでした。平安から鎌倉時代にかけて、西国観音霊場などの巡礼がさかんになると、仏教への信仰がそこかしこにひろがりをみせるようになります。すると、声明の節回しをベースに、親しみやすくおぼえやすいメロディーの歌が求められるようになりました。そして和歌のように短くて、意味を理解しやすい歌詞がつけられた「詠歌・和讃」が次々と生まれ、多くの人に親しまれお唱えされるようになりました。
私たちは、暮らしの中でいろいろな喜怒哀楽にめぐりあいます。そして、心のよりどころ、支えを求めずにはいられません。古来より、日本の美しい四季に彩られた風景の中には、人々の数だけ生活があり、数えきれない喜怒哀楽にあふれています。御詠歌は、そうした民衆のありったけの心がつめ込まれた音楽なのです。御詠歌のメロディは日本の風景を奏で、ご先祖さまから伝えられる魂を、音にして紡いでいるのです。