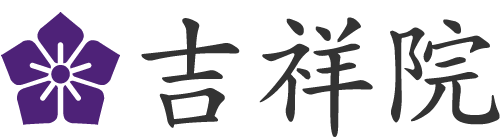風信(かぜのたより)No.81
さて、皆さんが仏さまの世界を感じる方法の一つに、仏の説法に耳を傾ける、その世界に響いている音声を感じ取り、受け止めるということがあります。でも耳で音を聴くだけでなく、全身、つまり五感でさまざまな響きを感じることが大事です。
その響き、音声には声明(しょうみょう)、そしてわかりやすい歌詞のご詠歌があります。響きによって、仏の教えを全身で体感するのです。

ご詠歌はお唱えするもので歌うものではありません。お経はむずかしくて意味がわかりにくいので、和歌のような七五調を基本とする言の葉にメロディーをつけました。ご詠歌の楽曲には、仏さまの世界を讃え、さらには亡き人の魂を鎮め、冥福を祈るものがたくさんあります。
仏さまの素晴らしさ、その世界に包まれた安楽な心地を、また亡きみ魂への底知れない悲しみとか、み魂が仏の世界で安らかなれと祈る想いを響きに変えて、その心を感極まって震わせます。ご詠歌をお唱えすると、心の奥深くにある想いをご詠歌の歌詞と旋律に乗せて、その空間に篤(あつ)い響きを創ります。お仲間と一緒なら多くの声が一つとなり響き合います。ご本尊さまの前でお唱えすれば、仏さまの世界と相まって厳かな響きとなり、仏さまの世界を感じられるでしょう。これを法悦とか法楽と呼びます。つまり、仏の教えによって生み出され、育まれる悦び、楽しみを身体全部で実感することになります。

抜苦与楽(ばっくよらく)というのはその言葉のとおり「苦を抜き、楽を与える」ということ。仏教でよく使われる慈悲のことです。慈悲は苦を抜いて楽を与える。「慈」は相手の楽しみを自分のこととして、「悲」は相手の悲しみを我がこととします。共に生きること。仲間が居れば、理解し合える人が居れば、たいがいのことは乗り越えられるでしょう。
心と心が共鳴する。人と人が響き合う。楽しいことも悲しいこと苦しいことも共に分かち合う。ご詠歌という言の葉とメロディー。言の葉は心にあるものを表現し、旋律で想いを響かせる。その響きが空間を震わせ、仏の世界を共鳴させ、その場に集う人たちに仏を感じさせてくれるのです。仏さまの慈悲の力に包まれる時、そこに悲しみは無く、楽しみの果てにある悦びに浴するのです。